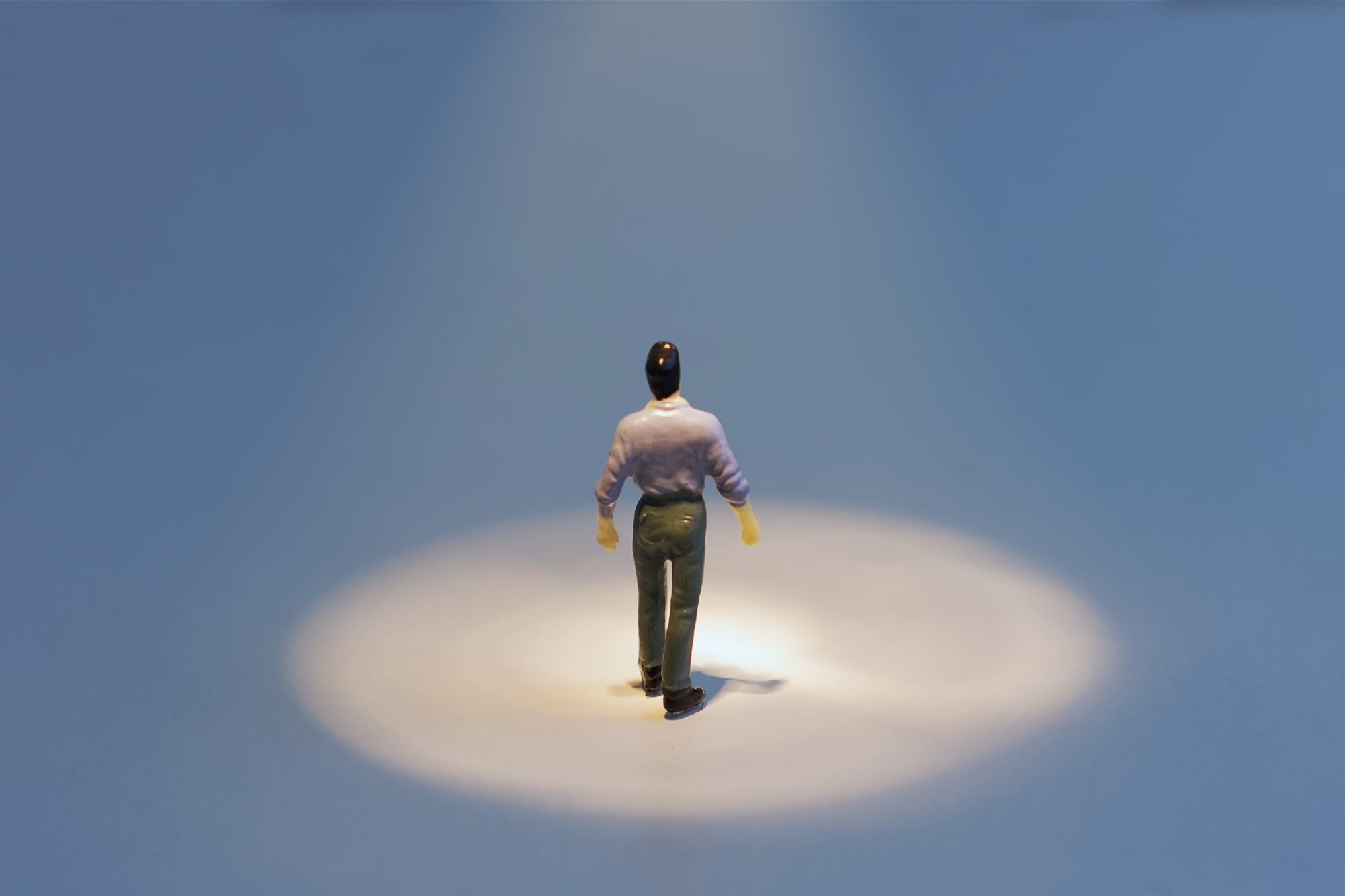健康に配慮した飲酒とは
2025.01.08
- コラム
- 健康
飲酒ガイドラインとは何か
お酒は私たちの生活に豊かさと潤いを与えるものである一方、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となります。更に、アルコール健康障害は、本人の健康の問題だけでなく、飲酒運転、暴力、虐待、自殺などの周囲への深刻な影響や重大な社会問題にも密接に関連していると言われています。
飲酒ガイドラインは、「アルコール健康障害対策基本法」に基づく計画の第2期計画(令和3~7年度) で作成されたものです。「アルコール健康障害対策基本法」は、平成25年12月に成立し、平成26年6月 に施行された日本の法律であり、国や自治体、国民、医療従事者などの責務が定められています。
アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めることで、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、国民の健康を保護し、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
上記の「アルコール健康障害対策基本法」に基づく計画で作成された飲酒ガイドラインは、国民一人ひとり がアルコールに関連する問題への関心と理解を深め、自らの予防に必要な注意を払って不適切な飲酒を減らすために活用されることを目的としています。
飲酒ガイドラインの内容
基礎疾患等がない20歳以上の成人を中心に、飲酒による身体等への影響について、年齢・性別・体質等 による違いや、飲酒による疾病・行動に関するリスクなどを分かりやすく伝えており、主に以下の 3つの内容となっています。
1.アルコールの代謝と飲酒による身体への影響
2.飲酒量(純アルコール量)
3.飲酒に係る留意事項

アルコールの代謝と飲酒による身体への影響
飲酒した際、飲んだお酒に含まれるアルコールの大半は、小腸から吸収され、血液を通じて全身を巡り、 肝臓で分解されます。アルコールの分解には、体内の分解酵素と呼ばれる物質等が関与していますが、体質的に分解酵素のはたらきが弱いなどの場合には、少量の飲酒で体調が悪くなってしまうこともあります。
また、アルコールは血液を通じて全身を巡り、全身の臓器に影響を与えるため、飲みすぎた場合には、様々な臓器が病気になる可能性があります。
特に、飲酒による影響には個人差があり、年齢、性別、体質等の違いによって、受ける影響が異なります。
◎年齢の違い
高齢者は、若い時に比べて体の中の水分量が減ってくるために、同量のアルコールでも酔いやすくなります。高齢者においては、飲酒による転倒や骨折の危険性が特に高まりますので、十分注意が必要です。
また、10歳代はもちろん20歳代の若年者についても、脳の発達段階であり、多量飲酒によって脳の機能が落ちるとのデータがあり、健康問題(高血圧等)のリスクが高まる可能性もあります。若い時と同じように飲んでいても安心できないということです。
◎性別の違い
女性は、一般的に、男性と比較して体内の水分量が少なく、分解できるアルコール量も男性に比べて少ないこと、女性ホルモンのはたらきにより、アルコールの影響を受けやすいことが分かっています。このため、女性は、男性に比べて少ない量かつ短い期間での飲酒でアルコールによる身体への影響が大きく現れる可能性もあります。近年はジェンダー平等の取り組みが進んできてはいますが、生物学的な性差はあるため、男性と同じように女性が飲酒をすることには注意が必要です。
◎体質の違い
ご自身もしくは周囲に、飲酒をすると顔が赤くなる人、俗にいう「お酒の弱い人」はいませんか。
そのような症状は、「フラッシング反応」によるものです。フラッシング反応とは、コップ1杯程度のビールなど、 少量の飲酒で起きる、顔や肌の赤み・吐き気・動悸・眠気・頭痛といった不快な症状を指し、この体質の人をフラッシャーと呼びます。
フラッシャーの多くは2型アルデヒド脱水素酵素の働きが弱い人です。エタノールからできたアセトアルデヒドの分解が遅いため、アセトアルデヒドが急激に体にたまることが主な原因となってフラッシング反応が起こります。2型アルデヒド脱水素酵素の活性の働きの強弱は、遺伝によるものと言われています。
人種は生物学的・身体的特徴で大きく3つに分類されますが、白色・黒色人種は100%が「活性型」といわれる中、日本人を含む「モンゴロイド系」の人種においては、活性型が56%、低活性型が40%というデータがあります。つまり、日本人の4割がお酒に弱い体質の可能性があるということです。
若い頃にはそのような症状があったけれど、今は症状なく飲酒できている人がいるかも知れません。フラッシング反応は当初不快感を伴うため、フラッシャーは飲酒を控える傾向にありますが、長年飲酒をしていると耐性ができて不快にならずに飲酒できるようになります。しかし、フラッシャーの飲酒者は、アルコールを原因とする食道がん等のリスクが非常に高くなるということもわかってきています。
過度な飲酒による影響
急激に多量のアルコールを摂取することにより急性アルコール中毒のリスクが高まります。急性アルコール中毒においては、搬送者の約半数が20代というデータがあることからも、適量飲酒を超えた無理な飲酒が若年者に多いことが分かります。
また、長期にわたる大量の飲酒は、アルコール依存症だけでなく、生活習慣病、肝疾患、がん等の発症誘因となりますので、過度は飲酒は控えた方が良いでしょう。
飲酒量を把握できるようにしましょう
これまでお伝えしたようなアルコール摂取のリスクを理解した上で、自分に合った飲酒量を決め、飲酒をすることが大切です。ここで、飲酒量の把握の方法を簡単にご説明します。
【お酒に含まれる純アルコール量の算出式】
純アルコール量(g)= 摂取量(ml) × アルコール度数(%) × 0.8(アルコールの比重)
例:ビール500ml(5%)の場合の純アルコール量
500(ml) × 0.05 × 0.8 = 20(g)
厚生労働省では、生活習慣病リスクを高める飲酒量(1日あたりの平均純アルコール摂取量)を男性では40g以上、女性では20g以上としています。
着目すべきは、単にお酒の量(ml)だけではなく、お酒に含まれる純アルコール量(g)です。
少量であってもアルコール度数が高いお酒を飲む場合には、十分注意が必要です。
飲酒量と健康リスク
世界保健機関(WHO)では、アルコールの有害な使用を減らすための世界戦略を示しています。また、飲酒量が少ないほど飲酒によるリスクが少なくなるという報告もあります。
例として、高血圧は少量であっても飲酒自体が発症リスクを上げ、大腸がんの場合は、1日当たり20g程度を超える量の飲酒を続けると発症リスクが上がるなど、ガイドラインには研究結果に基づく病気毎に発症リスクが上がる飲酒量が載っています。
飲酒による病気への影響には、個人差がありますので、一人一人が病気の発症リスクにも着目して、健康に配慮することが大切です。具体的には以下のようなことを心掛けると良いでしょう。
健康に配慮した飲酒の仕方等
① 自らの飲酒状況等を把握する
② あらかじめ量を決めて飲酒をする
③ 飲酒前又は飲酒中に食事をとる
④ 飲酒の合間に水(又は炭酸水)を飲むなど、アルコールをゆっくり分解・吸収できるようにする
⑤ 一週間のうち、飲酒をしない日を設ける
飲酒に係る留意事項
避けるべき飲酒として、不安や不眠を解消するための飲酒があります。不安の解消のために飲酒を続けることによってアルコール依存症になる可能性が高まったり、飲酒により眠りが浅くなることで睡眠障害のリスクとなります。
また、体調不良時や服薬中の飲酒は、普段よりも飲酒の影響が大きく身体に現れたり、薬の効果を増減させたりする可能性もあるため、控える必要があります。
今回は、飲酒ガイドラインについて解説しました。
ご自身の飲酒量の把握し適量飲酒にとどめることは、自身の健康に配慮することに繋がっていきます。
近年は、ノンアルコール飲料の種類も増え、以前に比べるとアルコールを摂取せずに他者とのコミュニケーションの場に参加することに対するハードルが下がったようにも感じます。
ご自身のためだけでなく、大切な周囲の人の健康を気遣う飲酒の仕方を目指していけると良いですね。
【参考文献】
厚生労働省 健康に配慮した飲酒に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001223643.pdf
e-ヘルスネット フラッシング反応
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/alcohol/ya-008.html
著者:金子 綾香
保健師
医療法人社団 平成医会
当コンテンツの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。