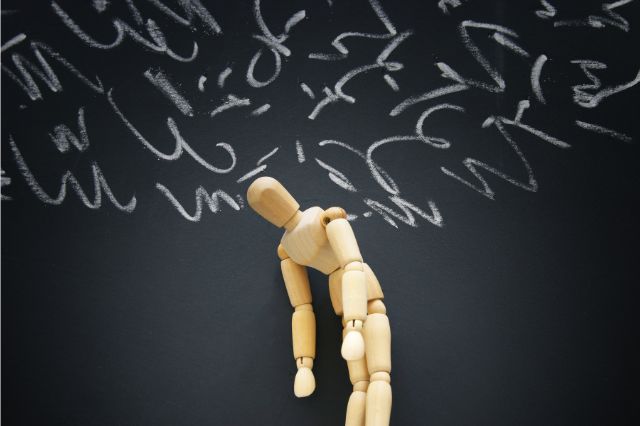HSP(Highly Sensitive Person)の特徴と向き合い方
2020.10.19
- メンタルヘルス

HSPについて
ひといちばい繊細で人の気持ちや外界の刺激に敏感な人を英語でHighly Sensitive Person(ハイリ―・センシティブ・パーソン)といいます。この頭文字をとるとHSPとなります。
HSPの概念は1996年にアメリカの心理学者エイレン・N・アーロン氏によって提唱されました。
この概念が世界中で認知されたのは、エイレン氏が執筆した『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。(原題:The Highly Sensitive Person)』という本が影響しています。
エイレン氏は、全人口の15~20%、5人に1人がHSPだといいます。
人間だけでなく動物までも一定割合でこの特性を有していることから、HSPにみられる特性は生物学的な生存戦略によるものだと考えられています。
HSPの特徴
HSPの人は、周囲の環境にとても敏感です。この気質を持つ人は職場や家庭などの中で気疲れしやすいことから、生きづらさを感じている方も多いのです。
HSPにはDOES(ダス)という4つの特性があります。
【Depth of processing 】 物事を深く考えて行動する
〇 多彩な観点から物事を考える
〇 調べ物をはじめると深く掘り下げることから知識量が多い。
【Overstimulation 】 過剰に刺激を受けやすい
〇 友達との時間は楽しいものの気疲れする。
〇 芸術や音楽に触れると感動しやすい。
〇 人の些細な言葉に傷つきいつまでも忘れられない。
〇 繊細なことに過剰なほど驚いてしまう。
【Empathy and emotional responsiveness 】 共感力が高い
〇 人が怒られていると自分のことのように感じて傷つく。
〇 悲しい映画や本などの登場人物に感情移入し、号泣したりする。
〇 人のちょっとした仕草、目線、声音などに敏感で、機嫌や思っていることがわかる。
【Sensitivity to subtleties 】 些細なことに気づきやすい
〇 強い光や日光のまぶしさなどが苦手
〇 カフェインや添加物に敏感に反応してしまう。
〇 肌着のタグやチクチクする素材が気になってしまう。
HSPを確認する方法
HPSは病気ではなく、生まれ持った感受性や気分の傾向などを指す心の特徴です。
HSPであるかどうか調べるチェックテストには様々なものがありますが、日本人の感性や特徴に適したもので「日本版HSP尺度(HSPS-J19)」があります。
刺激に対して敏感なHSPですが、約30%は刺激に対して強い欲求を持つHSS型HSP(刺激追求型HSP)であるともいわれています。

自分がHSPに当てはまったら
ここでHSPの人が少しでも楽になれるような考え方をいくつかご紹介します。
完璧な自分を求めすぎない
細かな点にもよく気がつくHSPは、完璧を求めるがあまり自分を追い込んでしまうことがあります。
完璧な自分というのは、必ずしも他者が敬意を払ってくれるわけではありません。欠点を克服しようと努力するのは良いことですが、過度に自分を追いこまず、自分の好きな面に目を向けてあげることで、生きづらさの解消につながるかもしれません。
責任を自分一人で背負い込まない
良心的で他者を責めることが苦手なHSPは、失敗したときや人間関係が上手くいかないときに責任を一人で背負いこみがちです。自分の責任を認められるのはHSPの良い点ですが、他者の責任や自分では対処できない影響を冷静に見きわめることが、過度な気持ちの落ち込みを防ぐ方法なのかもしれません。
他者との境界を設ける
共感力の強さが原因となって自分には関係のない問題を抱えてしまったり、仕事とプライベート問わず相談事や頼み事の多さに疲れ果ててしまうことがあります。
他者との境界をもうけ、自分軸で物事を考える意識を持つと良いかもしれません。
自分の思慮深さを理解する
他者の何気ない言動や行動に深く傷つくことがあります。
他者への気配りに長けていることは良いことですが、それが行き過ぎてしまうと自分を苦しめます。ほとんどの人が自分ほど周囲に気を遣っていないことを知り、他者の言動や行動を重く受け止めすぎない意識を持つことも重要です。
前述したように、全人口の15~20%を占めるといわれるHSPですが、逆をいえば約8割ものHSPでない人たちの中で生活していることになります。
HSPの敏感で注意深い特性は、内気や神経質といったネガティブなイメージと結び付けられやすく、社会ではたびたび誤解されことがあります。
しかし、物事の小さな変化にもよく気がつくので、私たちにおとずれる危機を敏感に察知し、その回避に幾度も貢献してきたということも事実です。思慮深く繊細で豊かな感性を持った人たちであるHSPは、私たちの社会にとって必要不可欠な存在でもあるのです。
皆さまの周りにHSPの傾向がある人はいませんか。そのときは、温かい言葉がけや配慮をしてあげてください。きっとあなたの力にもなってくれるはずです。
※当コンテンツの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。