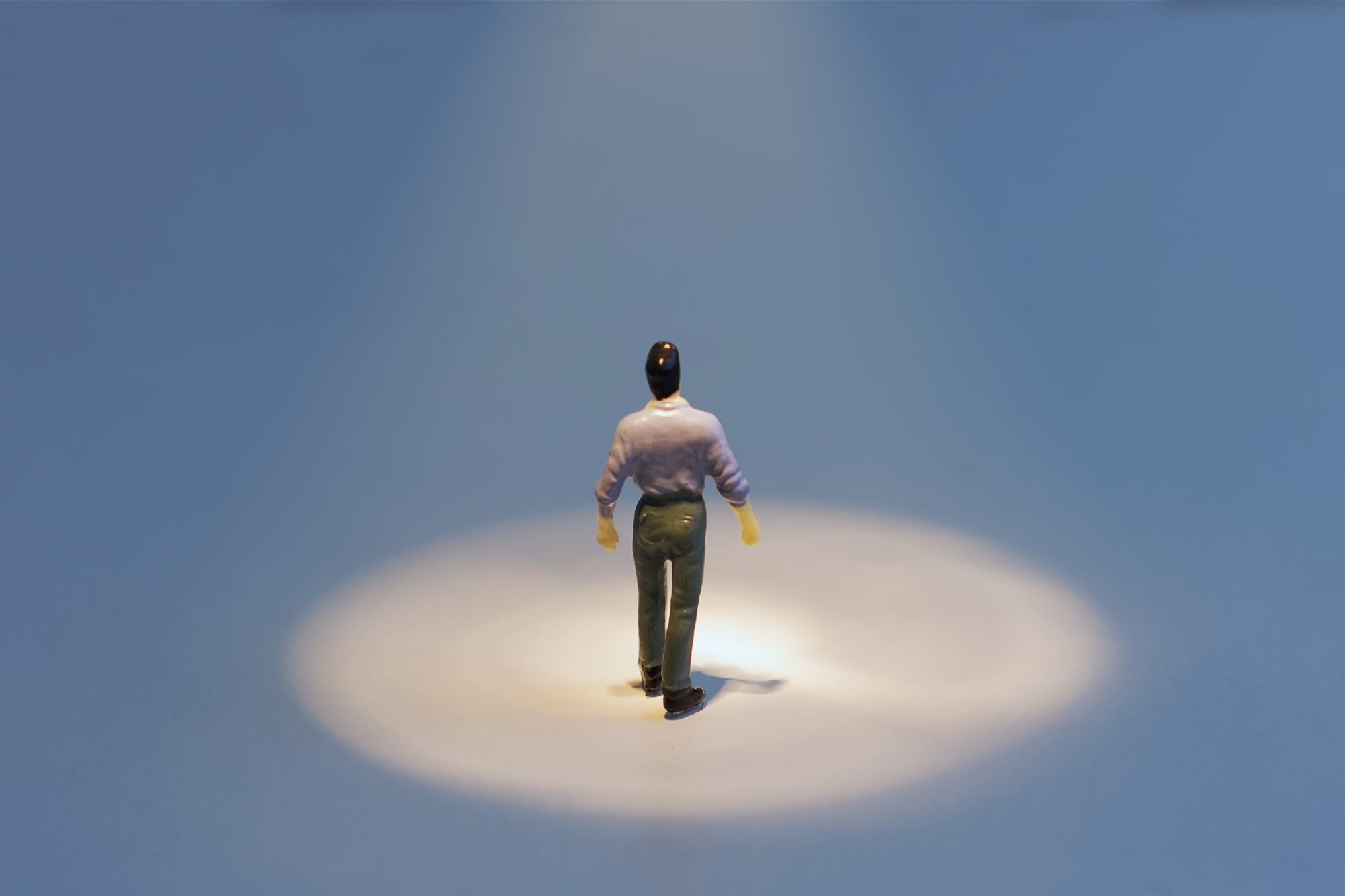『目の疲れとは』
2025.04.09
- コラム
- 健康
目の疲れと眼精疲労は同じもの?!
“眼精疲労”と“疲れ目”は同じものだと思われがちですが、実は違います。
疲れ目は一時的なもので、休息や睡眠をとれば自然に回復し、体への悪影響もほとんどありません。
一方、眼精疲労とは、視作業(眼を使う仕事)を続けることにより、眼痛・眼のかすみ・まぶしさ・充血などの目の症状や、頭痛・肩こり・吐き気などの全身症状が出現し、休息や睡眠をとっても十分に回復しえない状態をいいます。
最近は特にパソコンやスマートフォンなどを使用する機会が増えたため、これが原因の眼精疲労が増えています。眼精疲労の3大要因は、目の筋肉疲労・目の乾燥・ブルーライトですが、その他にも以下のような原因があります。
・目に負担のかかる環境(明るすぎや暗すぎる環境)
・近視・遠視・乱視・老眼
・眼鏡やコンタクトレンズが合っていない
・ドライアイ
・白内障や緑内障などの病気
・ストレス
全身疾患に伴うもの・心因性のもの・環境によるものなど、眼精疲労をもたらす要因は多岐にわたります。
原因を特定できれば、それをなくすことが必要です。眼鏡やコンタクトレンズが合っていない場合は作り直したり、目の病気があれば治療をします。パソコンやスマートフォンを使用する機会の多い人は、適度な休息を取ることが非常に大切です。眼精疲労に特効薬はありませんが、ビタミン剤の配合された点眼薬や内服薬が有効である場合があります。
◎ブルーライトとは
眼精疲労の原因にもなっているブルーライトですが、どのようなものが知っていますか。
ブルーライトとは、私たちが目で見ることのできる光(可視光線)の中で最も波長が短く、強いエネルギーを持つ青い光のことで、角膜や水晶体で吸収されずに、網膜まで到達します。
厚生労働省のガイドラインでは、ブルーライトの健康への影響を考えて、連続して1時間の操作を行ったときは、15分以上の休憩を推奨しています。
可視光線の波長の長さは、およそ400~780nm(ナノメートル)であり、400nmより短くなると「紫外線」、780nmより波長が長くなると「赤外線」と呼ばれます。可視領域以外の紫外線や、赤外線は人の目で見ることはできません。

ドライアイ
目の疲れや眼精疲労と同じくよく聞くものとして、ドライアイがあります。
涙には、目の表面に広がって崩れない性質がありますが、その性質が失われ、崩れやすくなり、目の不快感や見えにくさを生じる病気がドライアイです。日本で2200万人もの患者さんがいると言われており、さらに増加しつつあります。
ドライアイでは、目の表面を覆う涙液膜が崩れやすく、その下の細胞にキズができることがあります。
ドライアイの症状は「目が乾く」だけでなく、「目がかすむ」、「まぶしい」、「目が疲れる」、「目が痛い」、「目がゴロゴロする」、「目が赤い」、「涙が出る」、「目やにがでる」などがあります。
ドライアイの危険因子として、加齢、女性、長時間画面を見るようなライフスタイル、湿度の低い生活環境、エアコンの使用下、コンタクトレンズ装用、喫煙などがあります。他にも、病気の影響などがあります。
軽い症状は、市販の目薬で改善できることもありますが、眼科では、目薬を処方したり、専門的な治療をすることもあります。当然、画面を見る作業やコンタクトレンズの装用を減らしたり、エアコンを調整したり、加湿器を使うことも効果があります。
近年の子供たちの視力の低下
小学校でも一人一台のタブレット端末が貸与されたり、スマートフォンなどが若年世代へ普及したり、大人だけでなく、子供たちも画面を見て過ごす時間が長くなっています。
文部科学省が公表した令和6年度 学校保健統計の調査結果によると、裸眼視力1.0未満の者の割合は、学校段階が進むにつれて高くなっており、小学校で3割を超えて、中学校で6割程度、高等学校で7割程度となっているそうです。この割合は年々増加しています。
この結果を受けて、文部科学省では、子供の目の健康を守るための啓発・周知、屋外での体験活動等の促進等の視力低下予防のための取組など、学校保健の推進に取り組むことを予定しています。
若い間は目の疲れは感じることは少ないかも知れませんが、子供たちの将来のことを考えると、対策は急務と言えると思います。
職場における照度の基準(労働衛生基準)の改正
令和4年12月より、事務所において労働者が常時就業する室における作業面の照度基準が、従来の3区分から2 区分に変更されました。今回の改正は、照度不足の際に生じる眼精疲労や、文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる上肢障害等の健康障害を防止する観点から、すべての事務所に対して適用されます。「一般的な事務作業」については300 ルクス以上、「付随的な事務作業」については150ルクス以上であることが求められます。
◎ルクスとは
「ルクス(lx)」とは、照明の明るさを示す単位で、光源によってその場所(面)にどれだけ光が到達しているかを表しています。オフィス全体は明るくなっていても、パーテーションで区切られているデスク面など実際の作業面が暗い場合には規準を満たしていないこともあります。正しい照度を知るには照度計が用いられます。
作業環境の見直し
目の健康のためには、目にやさしい作業環境での業務が大切です。以下が望ましい作業環境です。
・姿勢 椅子に深く座り、床に足裏がつき、膝の角度は90度以上
・モニターの位置 目とパソコンの間を40cm以上とる。
モニターの上辺が目より数cm高くなるようにする。
・連続作業時間 1回の連続作業時間は60分以内。
その間にも10~15分の休憩を入れる
・室内の光 太陽光がモニター画面に入り込まないように、
カーテンやブラインドを使用する
どれも大変重要です。みなさんの日々の作業環境はどうでしょうか。
目のセルフケア
分かってはいても、なかなかPCやスマートフォンを見ないようにするのも難しいのではないかと思います。
そこで大事になってくるのが、目のセルフケアです。
▶1.目を休ませる(まばたき&遠くを見る)
目の疲れを取るためには、まず、まばたきを意識的に行うのがおすすめです。
まばたきには涙の分泌を促して眼球を潤す働きがあるため、意識的に行うことで、目の渇きを軽減することができます。また、まばたきをすると、目の周りの筋肉が緩み、目の疲れが軽減されます。
特に、デジタル機器の画面を見ているときは、まばたきの回数が減るため、意識してまばたきを行うのがおすすめです。
▶2.目のストレッチ
まばたきをしたり、ギュッと強く閉じたり、左右を交互に見たりすることが目の筋肉を緩めるストレッチになります。
▶3.目元を温めて血行促進
40度くらいの蒸しタオルを使ったアイパックは疲れ目やドライアイに効果的です。
市販のアイパックも色々ありますので、活用すると良いかと思います。
▶4.点眼薬を活用する
目の疲れに特に有用なビタミンとしては、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12などのビタミンB群とビタミンEが挙げられます。
ビタミンB1は、エネルギーの代謝や神経の正常な働きに欠かせない栄養素で、目の筋肉の疲れを軽減したり、目の神経(視神経)を活性化したりする働きがあります。また、末梢神経の修復に関与するビタミンB6や神経の健康維持に欠かせないビタミンB12も、視神経に働いて疲れ目を和らげてくれる栄養素です。
ビタミンEには、体中の血液循環の改善に関わるとともに、抗酸化作用によって細胞をダメージから守る働きがあります。そのため、目の周りの血行をよくするとともに、眼球の細胞をダメージから守る役割を果たしてくれるので、ビタミンEの摂取も疲れ目に効果があります。
今回は目の疲れと、その対策について解説しました。
眼精疲労にならないように、日々の作業環境を見直したり、セルフケアを心掛けていけると良いと思います。
著者:金子 綾香
保健師
医療法人社団 平成医会
当コンテンツの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。