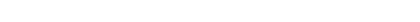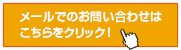- 義務化というけれど、実施しない場合には何か罰則規程があるのでしょうか?Answer
A. 労基署への年間書類の中に実施状況の報告を入れることが想定されています。50名以上の事業所で実施していないと「指導」が入ります。検討会の議論では、ストレスチェック実施は義務、集団分析も一定規模以上は義務、職場改善は努力規定になりそうです。
ストレスチェックを実施せずにメンタル不調の労災申請が発生した場合には、会社は極めて不利な状況になります。
- 50名未満の会社は努力義務ということですが、実施しなくても良いのでしょうか?Answer
総従業員数が50名以下の会社であれば、努力義務になります。努力義務とはいえ義務化となりました。
小規模な事業所こそ、一人一人の影響が大きいことから、メンタルヘルス対策がより大切と考えます。
- 事業所人数のカウントについて
- 正社員だけではなく、週1回しか出勤しないアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者としてのカウントに含めます。
- 全社的には50人を超えるが、支店ごとの従業員は50人未満の場合には義務になるのでしょうか?Answer
A. 事業所の在籍従業員数を付け替えている可能性などを行政機関が調査する可能性があります。また、公共事業や行政の業務を受託している場合は、産業医選任と同様ストレスチェックの実施を求められる場合があります。
- ストレスチェックと健康診断は、合わせて実施したほうがよいのでしょうか?
それとも個別に実施した方がよいのでしょうか?Answer
A. 「法定検診」は従業員が受診することが義務となっています。一方で「ストレスチェック」は従業員に検査を受ける義務は発生しません。
同時に実施する場合には、両者を明確に区別して実施するならば、同時実施は可能です。
- ストレスチェックを外部委託した場合、ストレスチェック実施機関の医師等と産業医とのかかわりはどういうものになるのでしょうか?Answer
A. 実施者は委託先外部機関になるので、煩雑で専門的な多くの役割(テスト項目の提示確認、評価基準の設定、テスト実施と実施状況の把握、結果評価集団分析と結果提供、専門機関の紹介など)から解放されます。産業医は「共同実施者」として外部委託先からの実施状況の報告などを密接に連携する事になり、労働者の申し出による「高ストレス者の面接指導」を中心に活動することになります。
労働者の情報提供の承諾が得られた結果だけを産業医は把握するので、従来の産業医と事業者の情報共有が出来なくなる不整合は生じません。
- ストレスチェックだけやれば、メンタルヘルス対策になるのでしょうか?Answer
A. ストレスチェックはセルフケア職場環境改善に向けた一次予防に関するものに限定されています。
一次予防では個人の判定結果に対するフォローと集団分析に基づく職場環境改善への取り組みが必要です。
しかしストレスチェックは「不調者発見が一義的な目的でない」と位置付けています。
国は「法定外として任意に鬱病等の精神疾患スクリーニング(2次予防)を行うことには事業者の裁量に任せること」としています。
職場の停滞感や労使紛争の予防、休職・復職の複雑な判断プロセスを真剣に検討するならば、メンタルチェック(義務化1次スクリーニング)と併せて2次予防のスクリーニングテストの並行実施をお勧めします。
2次スクリーニングで受診勧奨者は会社を通さなくても無料で医師面談を受けられるような仕組みが、早期発見早期治療には有効です。
そして休職者と復職者支援(3次予防)プログラムも整備することを目標にして下さい。
- 事業者に ストレスチェックの結果を保存義務はあるでしょうか?Answer
A. 「個人のストレスチェック結果」の保存は、外部委託をすれば外部実施者が5年間の保存義務を果たします。「集団分析の結果報告」は事業主に5年間の保存の義務があります。
- 仕事の軽減を狙って、すべての項目で重い判定を得たいと回答を操作する労働者が出てくるかもしれません。また、質問にある問題をほとんどいつも感じていても、逆に「ほとんどなかった」と回答してしまいます。 このように労働者が誠実に回答しないようなケースでの判定結果の取扱いとその後のフォローはどのように行っていくのでしょうか?Answer
A. 国はこのテストの目的を「不調者の発見を一義的な目的に置かない一次予防(セルフケアと職場環境改善によるメンタルヘルス不調の未然防止)」と法律で明示しています。
本人のストレスに対する気付きを促しているので、高ストレスの結果となった場合にも本人が会社への医師の面接指導希望の申し出が行われて、はじめて面接が行われることになります。
- 雇用不安を覚えるような職場では、本当のことを回答しないのと同じように、医師による
面接指導などはあえて避けようという人が多く出るのではないですか?Answer
A. 会社の安全衛生委員会でストレスチェック結果による「不利益取り扱い」防止を審議することが義務づけられています。
- ストレスチェック制度の導入を受け、安全・衛生に関する定めとして就業規則にはどのように記載することが望ましいのでしょうか?Answer
A. 現時点での一案として考えられる例を示します。(あくまでも一例です。実際に作成される際には、貴社内でご検討下さい。)
第〇条 会社は、従業員に対し、毎年1回、法令に基づく心理的な負荷の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う。
2 会社は、前項の検査を受けた従業員のうち、法令の要件に該当する者が希望する場合、医師による面接指導を行う。
3 前項の面接指導の結果、会社が必要と認めるときは、当該従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずることがある。
- 健康診断のようにストレスチェックの 実施報告を労働基準監督署へ行う必要はあるのでしょうか?Answer
A. 以下の項目について実施報告が必要です。
- ① ストレスチェックの実施年月
- ② 在籍労働者数
- ③ ストレスチェックの受検人数
- ④ 面接指導を受けた労働者数
- ⑤ 実施者
- ⑥ 面接指導を実施した医師 ⑦集団分析実施の有無